<ものすごく的を射た落語論>頭木弘樹著「落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ」
高橋秀樹[放送作家/発達障害研究者]
***
頭木弘樹著「落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ」(ちくま文庫)は、タイトルを見ただけで言いたいことは一目瞭然の本である。予想の通り「実は、落語には結構面白いところがあって、それはこうだから」をわかりやすく解説した、必聴リスト付き落語再入門ガイドだ。
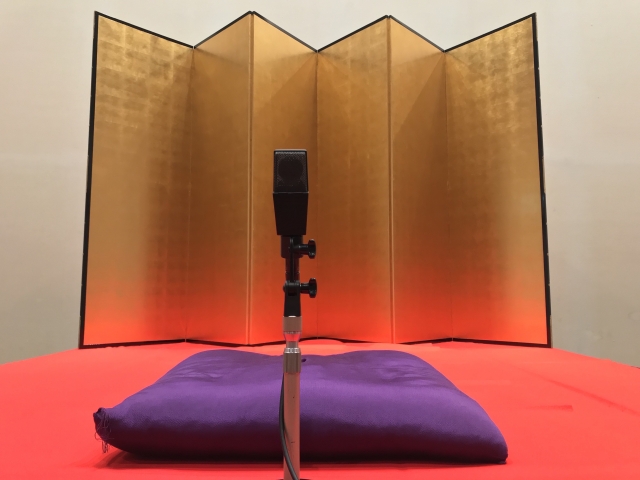
冒頭の「人にすすめられて落語を聞いた人の感想」というのがまず笑える。以下のようなものであるという。
* 落語を聴いて、すぐに「面白い!」となる人はまずいない。
* 面白くなくもないけど、また聴くほどではないかな・・・。
*どちらかと言えば、面白くないかも・・・。
* 何が面白いのか、さっぱりわからない。
落語は今、人気だったり、一過性のブーム(春風亭小朝)だったりするが、新規ファン獲得にはこういうハザードが確かにあると、筆者も両手を挙げて同意する。
筆者は昭和30年(1955年)山形の生まれで、テレビで見る笑いは大好きだったが、落語はラジオでしか聴いたことがなかった。ラジオで聴いたのは古今亭志ん生や桂文楽などの名人上手だった。早稲田大学の文学部に進み、何はともあれ、あこがれの落語研究会に入った。つまり、落語好きを自認していたというわけだ。
ところが、クラブの先輩に言われて、寄席という所を訪れて変な気がした。「寄席で聞く落語が本物」という考えが先輩にはあったと思う。噺家の名前は忘れたが、新宿・末廣亭で聞いたのは爆笑が約束されているネタ「長屋の花見」である。しかし、そこでの感想は、「あれ、落語って意外と面白くないぞ。こんなはずじゃないと思うけど」だったのである。
その後もトリまで、色物を挟みながら、噺家がどんどん出てきたが「こんなはずじゃない」「こんなはずじゃない」と思い続けたのを覚えている。膝替わりで手品のアダチ龍光が登場したときはほっとした。客席も筆者も拍手をして、しかも笑った。
その時がたまたま下手な落語家だったのか? それが理由ではないことが今なら分かる。筆者は落語ではなくストーリーを聞いていたのだ。一生懸命、理解しようとして落語を聴いていたのだ。ストーリーの展開は? 落ちは? 特にこの「落ち」というのが鬼門だ。
たとえば「長屋の花見」の「落ち」は以下のようなものだ。
卵焼きに見立てた「たくあん」をかじり、お酒に見立てた「お茶け」を飲みながら、貧乏長屋の面々が花見で大騒ぎ。そのうちのひとりが大家さんに、湯呑の中をじっと見てこう言う。
月番「大家さん、近々長屋にいいことがありますよ」
大家「どうして」
月番「酒柱が立っている」
まあ、落ちとしてはレベルの高い方か。「落ちの意味は分かったけど、大切な落ちなのにたいして面白くないなあ」と思わないだろうか。本書の著者、頭木弘樹はこう言っている。「落語の命は『落ち』ではない」「『落ち』で、本当に大切なのはそれ自体の面白さではなく、噺をそこで終わりに出来る役割であるから」。そのとおりである。
筆者はコント作家になって師と仰ぐ萩本欽一に何度も何度も言われたとがある。
「君らは、落ちばっかり考えている。落ちなんかどうでもいいんだよ。設定だ設定。人物がひとりでに動き出す設定を考えろ。落ちは終われればいいんだから、落ちなんかなくてもオレが終わらす」
落語の紹介には大抵「落ち」まで書いてある。最も大切なら、「落ち」には言及してはならないのではないか。ミステリの「落ち」を書くのは重大なルール違反だが、落語の「落ち」は書いてもいいほど軽いものなのだ。ちなみに早稲田の落語研究会は「おちけん」とは呼ばない。「らっけん」である。「落ち」の研究会ではなく、「落語」の研究会だからである。実演よりも鑑賞が重要視される。
さて、著者の頭木弘樹は、20歳のときに難病になり、13年間の闘病生活を送っており、そのときから落語を熱心に聴き始めたという。本書を読むと、その熱心さが半端でないことがよく分かる。さらに、彼に惹かれた理由は、登場・引用される研究者・小説家が筆者の趣味とほぼかぶっているからである。太宰治、芥川龍之介、澁澤龍彦、安部公房、深沢七郎。きっと、誰も知らないだろう早稲田「らっけん」会長・興津要教授も登場する。
なお、早稲田の「らっけん」の基本文献は、暉峻康隆「落語藝談 文楽・正蔵・円生・小さん」、興津要「異端のアルチザンたち」、桂文楽「あばらかべっそん」、古今亭志ん生「びんぼう自慢」、三遊亭圓生「寄席育ち」などであった。
断っておくが、読んだからと言って落語が好きになるわけではない。ただし、頭木弘樹はこれらすべてを読んでいることが覗える。
それからもうひとつ必読文献がある。立川談志の「現代落語論」である。パート2まであるが、この中で談志は「落語とは、人間の業の肯定」だと言っている。辞書で引くと「業(ごう)」とは、「理性によって制御できない心の働き」のことだ。
(談志)「立川流創設の頃まで、あたしは〈人間の業の肯定〉ということを言っていました。最初は思いつきで言い始めたようなものですが、要は、世間で是とされている親孝行だの勤勉だの夫婦仲良くだの、努力すれば報われるだのってものは嘘じゃないか、そういった世間の通念の嘘を落語の登場人物たちは知っているんじゃないか。人間は弱いもので、働きたくないし、酒呑んで寝ていたいし、勉強しろったってやりたくなければやらない、むしゃくしゃしたら親も蹴飛ばしたい、努力したって無駄なものは無駄…所詮そういうものじゃないのか、そういう弱い人間の業を落語は肯定してくれてるんじゃないか、と。」
これと同じことを頭木弘樹は落語「らくだ」を例に挙げながらの登場人物が飲んだくれで、絶望的な状況の人ばかりとした上で、こう述べている。
「落語から笑いを取り去ると、じつはかなり絶望的な状況が描かれていることが多い。貧乏のどん底とか、ギャンブルがやめられないとか、女や男に騙されたとか、酒で一生をだいなしにするとか・・・。それが人間というものだと。笑って語るのが落語の大きさ」
頭木弘樹は、談志には言及していないが、聴き手と演者違うところから出発して同じ所にたどりついたようだ。講談が「読む」「語る」なら、落語は「話す」。まあ、偉ぶっても、説教しても人間てのは、しょうがないってものだと筆者は思っているが。
【あわせて読みたい】
