いま、喜劇を作り続ける理由
大森ヒロシ[俳優/演出家/劇作家]
***
芝居コントを続けている。この道に入って 33 年。2009 年に立ち上げた大森カンパニープロデュースはコロナ禍の中 12 年目を迎え、先日 8 月 8 日に 37 本目のプロデュース公演『更地 16』の千穐楽を終えた。年平均3本のプロデュース公演は大人の芝居コント『更地』『更地 SELECT~SAKURA』の 2 本と、昭和の匂いを多分に残した人情喜劇 1 本で構成される。12 年間で 38 本のプロデュース公演。これは個人プロデュースとしては突出している本数である。
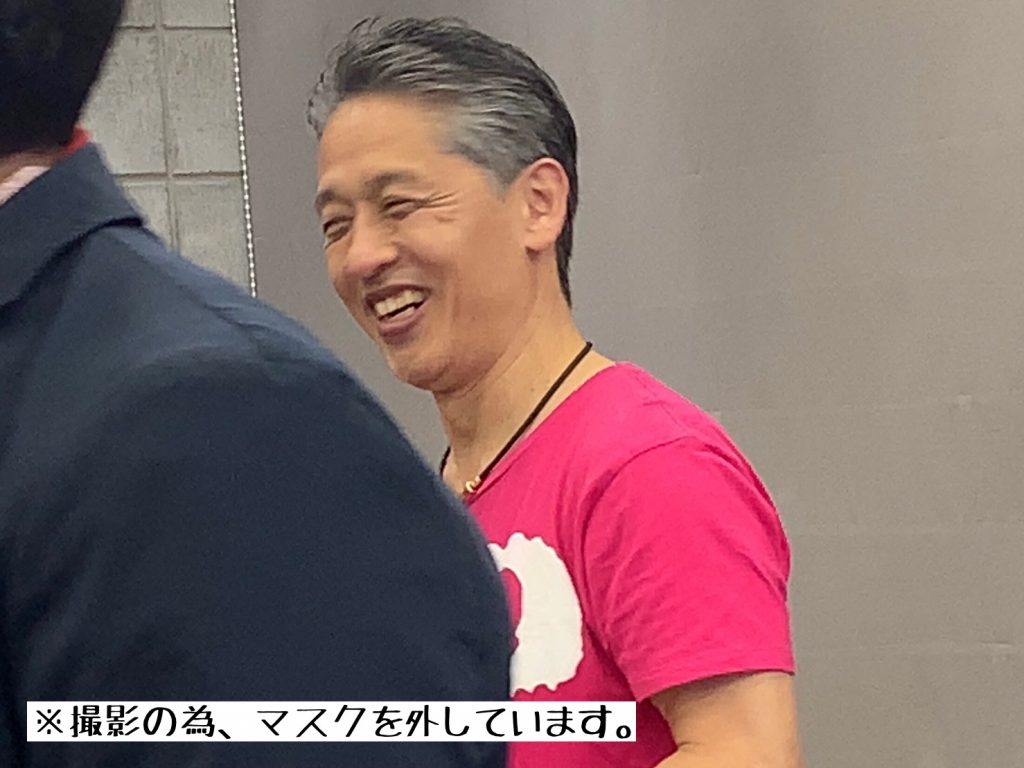
全く有名ではないのによくここまで続けて来られたと思う。沢山の人に支えられて来た。「有名人は何をやっても OK。無名な人はその何倍も頑張らないとだめ」大将(欽ちゃん)からは沢山の事を学ばせて頂いた。
「何故続けられたのか」と問われればそれは単純に「好きだから」としか言いいようがない。自分が面白い、楽しいと思うことに共感してくれる仲間がいて、足を運んでくれるお客さまがいて、みんなが笑顔になれる。実に楽しい。どんな時代でも笑いや笑顔は必要だ。
「芝居コント」聞きなれない言葉だと思う。テレビで芸人がやるコントと一線を画した役者によるコント、それを芝居コントと定義付けている。『更地』とはその名の通り、大道具が何もない舞台で机や椅子と言った簡単な小道具だけで展開される芝居だ。12~13 本のオムニバス形式だが、登場するキャラクターが別なコントで登場したり、ストーリー的に関連性があったりと 10 数本で 1本の芝居として構成している。
コントは短い喜劇。喜劇の核は「真面目にやる」こと。「笑い」と「お笑い」を敢えて区別して、舞台での「生」の「笑い」作りにこだわっている。稽古では「笑い」を緻密に作り上げる。身体の動きは勿論、間、音の強弱、高低、うねり、語尾の上げ下げに至るまで徹底的に稽古する。
「間」というと、細かい時間の長さと解釈する人がいるが、単に時間の長短で「間」を掴もうとしても一生掴めないと思う。基本は会話だ。「間」は実は喋っている時間である。必ず心の中で喋っている。「間」のことを言われると「長さを気にして会話が出来なくなる」と言うのは愚の骨頂で、「間」は呼吸であり「笑い」は芝居だ。
「笑い」を作る緻密さは時に「大森地獄」と称される。しかし、ありがたいことにこの「大森地獄」への参加希望者は後を絶たない。芝居作りの大原則「その時、その場で初めて聞いて、初めて見て、初めて喋る」ここが肝要である。緻密に作って本番では柔軟に対応する。長編でも短編でもそれは不変。それが喜劇を続けるカンパニーとしての基本コンセプトだ。
なぜ、役者でコントを作るのか。役者は「笑い」に対して「真面目に」取り組むから。「笑い」に対して妙な先入観なく、芝居、喜劇として取り組むからである。なまじ笑いを経験している人は自分でシュートをしたがる。その気持ち良さを知っているから。それは勿論理解出来るし否定もしない。が、得点はチームのものだ。誰がシュートしたって良い。大切なのは良いパス回し。良いパスを回せる技術があるのだからいいパスを回せばいい。誰かがシュートを決めて作品全体の得点にする、笑いを生む。自分の役割を把握し調える。その事を分かっている集団のコントは実に面白いのだ。
笑いの技術や方程式なんか分からなくても良い。ブレずに真面目にやる。慣れない、ふざけない。もっとも、ふざけることを許容することはないのだが。プロなのだから、「笑われる」のは恥ずかしい。「笑わせる」のが当たり前という言葉をよく耳にするが、「笑わせる」というのはいささかおこがましい。
プロであるならば、その上の「笑い」を作らなければならない。舞台は劇場に時間とお金を使って観に来て下さる方がいて初めて成立するものである。その有難さを決して忘れてはいけない。
お客さんは最後のピース。同時に板の上の役者に様々なことを教えてくれる。幕が開いてから昨日と全く同じことを繰り返すのであれば映像を撮って流せばいい。その時、その場で流れる時間、空気を大切にし、そこで呼吸をし、動く。
カンパニーでは幕が開いてからも日々稽古を重ねる。幕が開いてお客さんが教えてくれたことを芝居に反映させたいからだ。これも大森地獄と称される所以。甘んじることなく更に研鑽を重ねる。それは客に媚びるという事ではなく、教えてもらったことを稽古し、本番を重ねることによって芝居を進化させ、深化させて、ブラッシュアップさせて行くのだ。
いらした方に常に最上のものを提供する。それはプロとして当たり前の事だと思う。ここを怠けてはいけない。芝居でも生き方でも「ラクをしない」大将から受けた薫陶の一つである。
しかしながら、昨年来のコロナ禍で演劇エンタメ界を巡る情況は一変した。特に喜劇は客席の密集度が笑いを増幅させるものだ。満員の客席、何が始まるのかとワクワクする期待感、高揚感。笑いは笑いを呼び、連鎖し膨らみ波となる。それに呼応して役者は熱を帯び、客席との得も言われぬ一体感を生み出す。
客席のソーシャルディスタンス、収容人数制限はそこに大きなブレーキをかけている。致し方ないことと理解はしているが忸怩たる思いは拭えない。
生配信というコンテンツも当たり前になった。考えてみればテレビの生中継のようなシステムだ。様々な要因で劇場に足を運べない方にはかなり有効な手段であると思う。一方、「舞台は、やはり生で」という思いはある。この空気感をカメラの向こうに伝えるにはどうしたら良いか。配信スタッフは、舞台中継のように撮影してカット割りして流すだけではダメだと認識してくれている。
この臨場感をどうやったら観ている側に届けられるのか、どこまで届けられるのか、研鑽を重ねている。昨年、1回目の緊急事態宣言(もはや緊急事態が常態化しているが、それはさておき)後、初めて配信に挑戦した時とは技術的にもかなり進化して来ていると思う。
コロナ禍での生の舞台で一番つらいこと。それは声を出してはいけないと言う意識がお客さんに働き、笑いを抑えてしまうこと。2回目の緊急事態宣言解除後に上演した舞台ではその傾向が顕著であった。前半、役者として出番がない時は客席後方でお客さんの肩越しに舞台を観ていた、演出家として。お客さんの肩が揺れているのは分かる。しかし声にならない。笑い声が劇場に響かない。これには参った。悲しかった。
客席の反応をもって板の上で教えて頂くのにそれが出来ない。板の上から全てのお客さんの顔を見ることは出来ないし、しかも顔の半分以上はマスクで覆われているのだ。声がないのは正に生き地獄だった。
ほとんどの劇場・公演団体の感染対策は徹底している。今は通常の舞台での感染拡大はほぼないと証明されて来ていることもあってか、「笑い」を巡る情況も徐々に戻って来ているがこの先、遠のいた足はなかなかすぐには戻らないだろうと覚悟もしている。劇場でマスクをせずに、心置きなく大声で笑えるのは果たしていつになるのだろうか。
そしてこの状況で、いつまで続けられるのか。終わりの見えない持久戦を強いられている。だが、勝たなければならない。
『どんな時代であっても、笑いは負けない』
これは先日上演された『更地 16』のキャッチコピーだ。劇場という場所、笑い声は人の気持ちを豊かにすると私は思っている。しばし日常を離れ、観劇に没頭し笑いで昇華して行く。
決して不要不急などではなく、文化芸術、エンタメは必要だ。芝居は娯楽だと思っている。最高の娯楽だ。惜しむらくは、お見送りが出来なくなり、劇場を後にするお客さんの顔が見られない事、声が直接聞けなくなってしまった事。そして観に来てくれた役者仲間と酒を酌み交わしながらの芝居談議が出来なくなった事。そこに何某かのヒントを頂く時もある。全く出来なくなった。公演後の大きな楽しみがなくなってしまった。
次回公演は 10 月 15 日から 24 日まで下北沢小劇場 B1 にて新作人情喜劇を上演させて頂く。コロナ禍 5 度目の公演。また稽古期間中から毎日、キャスト・スタッフの発熱連絡に怯えることになる。今、感染者は勿論、発熱者や濃厚接触者が関係者に出れば稽古や公演は中断若しくは中止となる。後手後手の政策で、今後演劇エンタメ界に対して如何なる方針が発出されるのか、こちらにも戦々恐々である。
大森カンパニーは、過去4度、稽古期間 1 か月~公演千穐楽後2週間。約2ヶ月に渡る健康観察でキャスト・スタッフ・観客からの体調不良報告は受けていない。これ即ち芝居の、笑いの神様が「もう少し続けて良いよ」と言ってくれているものだと勝手に解釈している。
少しでも怠けてラクをしたら「はい、おしまい!」とシャッターを下ろされる気がしてならない。これからも「真面目に」喜劇に取り組んで行きたい。
笑うことは必要だから。
過去の上演履歴は大森カンパニーホームページをご覧下さい。
次回作は大森カンパニープロデュース vol.38人情喜劇シリーズ第 11 弾「おおばこ」。脚本・演出:大森博。出演に坂本あきら・山口良一・杉本有美らを迎える。10 月 15 日~24 日 下北沢小劇場 B1 にて。9 月 16 日~前売り開始!
【あわせて読みたい】
